アクセスくださり、誠にありがとうございます!
こちらのページが検索で表示されますので、
読んでいただき、ありがとうございます・・
私はただの個人ブロガーでして、教育相談をしているだけですので、
業者でもありませんし、斡旋もしておりませんので、ご注意ください!!
有益な情報をダダ漏れしておりますので、今までの記事をよく読んで
大事な情報を掴んでくださいね!
経験に基づいて書いていますので、ちょこちょこと大事なことが隠れていますよ!
親子留学のすすめの本をぜひお読みください。
では以降をお読みくださいね!
親子留学をはじめるにあたって、
まず安全面を重視して、進めることが大事です。
ベルリンの公式ホームページは、こちらになっています。
すべての情報はここに基づいています。
今現在は、無料のDeepLで翻訳ができ、
またPDFも翻訳可能ですので、
上手に利用されてください。
親子留学を1年でも、ちょっとの期間でも
子供に経験をさせたいという方が増えてきました。
最低でも1年間は親子留学をして、
将来的に役立つ何かを得て帰国をしたいものですね。
ドイツは、英語圏、オーストラリア、ニュージーランド、
カナダ、などのように留学が国の主要な産業ではないので、
留学生というのは、高校の一部と大学生以上になります。
英語圏、オーストラリア、ニュージーランド、カナダなどは、
留学生を推奨していて、留学産業が国の主な産業であるとも言えるのです!
小学生、中学生などは、親と一緒にドイツに来るようになります。
一部のインターナショナルスクールでは、14歳からボーディング制度があります。
親と海外に出ることを全般に、親子留学、もしくは、移住を目的として、
親子移住、教育移住とか現在では呼ばれています。
8年前くらいから、子供の進路の1つとして、
賢い親御さんたちの間で、親子留学、教育移住などの
ニュアンスで捉えられて来たと観察しています。
今の時代、親子留学にチャレンジしてみる、
そこから、子供の可能性を広げてみる・・ということは、
非常に大事になってきているのかもしれません・・・。
親子留学について。考え方・進め方はどのようにすればよいのか?
親子留学をおすすめしますが、そもそも、親子留学とは・・・
子供だけが単身で留学するのと違い、親と一緒に留学することです。
親子留学のメリットは、
- 子供いつも寄り添い、子供の精神的安定になり、安全
- 子供の将来的に進む道、現地の大学や永住権まで目指すことができる
単身留学であれば、親がその国に長期滞在できるビザがないので、日本で帰国するのを待つしかありません。
英語圏などでは、単身で大学に進み、永住権を取得する方もいらっしゃいます。
親子留学ですので、その後、長期滞在を目指すことができますが、移住ではありませんので、いつかは、日本に帰国することを意味している方もいらっしゃいます。
英語圏などは、長期親子留学をしている方も多く、しかし、永住権などはなかなか取得できませんので、帰国になる方も多いようです。
教育移住(長期親子移住)とは・・・
子供の学校や教育のために、ある国の就労ビザを取得して移住することです。
移住ですので、長期間の滞在を意味しています。親がビジネスをして、その国で長期に移住している方も多いようです。
オランダ移住、ハワイ移住などが検索をすると出てきます。ドイツ教育移住もアリかと思います。
長期にわたり、子供の学校や教育のためにその国に滞在して子供の学校卒業、大学入学、そして、その国の永住権を目指していくことになります。
親は、子供のために、その国のビザを取得、更新しなければいけません。
親子留学と教育移住の違いとは・・・
親子留学は、いずれ日本に帰国することを意味し、教育移住は、移住した国に長期間滞在して、永住権を取得していくことを意味しています。
親子留学が長期になると、教育移住のニュアンスが増えていきます。
このあたりは、言葉のニュアンスですので、どちらでもよいことになります。
しかし、興味深い点は、親子留学は、わりと肯定的にとらえられているようです。子供のために勉強をしにいくのです・・というニュアンスです。そして、いずれは帰国を予定していますというふくみがあります。
反対に、教育移住など、移住が入ると、親子の場合は、イメージ的にあまり良くないニュアンスがあるということです。帰国せずに、そのまま海外移住するのですか?というニュアンスのようです。
日本語のおもしろいところでもあり、言葉をこえて本質を捉えることが大事だということがよくわかります。
私のサイトでは、親子留学と表現している場合が多いです。長期でも短期でも、親子留学として捉えています。
長期の滞在と数年(ビザが更新できない場合の1−3年くらい)の比較をしています。
10年目からみる、親子留学、教育移住、留学について考えること!
個人的な考え方、価値観を言ってみるならば、余裕がある方は子供さんを英語圏に単身留学させた方が良いと考えますし、親子留学でガーディアンビザでもいいので、まずは英語圏に行くのが良いと考えています。
最低1年でも海外に行くことで、将来的には良い影響があると考えます。それは、語学の面だけではありません。視野が広がるというのは当たり前なことで、それよりも、日本の環境を鑑みるに、日本を少しでも離れて見ることが大事です。今の時代での留学、親子留学などの価値は、こちらの方に重きがあると考えています。
我が家は2020年で親子留学10年目になりますが、親子留学をして、振り返って思うことは、やはり、親子留学をしてよかった!と断言をしたいと思います。日本の狭い世界の中だけでなく、10歳まで日本で子育てをして、海外に出たのは正しかったのではないか・・と考えています。
日本にいる間は、私自身かなりの教育ママで東京の首都圏におりました。このまま日本の受験に塗れていくのかな・・と思いつつ、その中でも塾などから離れて、自力でできるようにさせたい、そして大学院こそはアメリカに留学かな・・と思い巡らしていましたが、
突如として311が起こりましたので、安全を期して、急遽息子の野球も辞めさせて、海外への道を選択することになったのです。あの時に気がついた方はわずかだったと思いますが、オーストラリアでは同じ思いのお母さんたちに多く出会いました。
日本で子供を大学まで進ませること・・これは、親自身も経験をしていますので、だいたい見えているものです。しかし、海外で子供を教育させることは、親自身も経験がないので、チャレンジです。不安や心配があるかもしれませんが、このチャレンジをしない人生、子供にチャレンジをさせない人生・・・これはちょっと力量不足なのではないか・・と思ってしまいます。
今思えば、勇気を出して、(そんなに深くは考えませんでしたが・・)自分の思うままに進んで来てよかったと思っています。深く考えたらできなかったと思いますし、子供のことを第1に考えて、しなければいけないことを大事にして進んで来てよかったと思っています。
我が家はどのように親子留学を進んで来たのか?
我が家の1年目は、ビザランという方法でしたが、そこから、オーストラリア親子留学でガーディアンビザ(保護者ビザ)を取得して、オーストラリアに3年滞在しました。
その後、ドイツに移行します。ドイツでは、最初個人事業主のアーティストビザを取得しました。自分が可能な多くの作品を提出して、これだけしかできないというのではなく、どんな活動でもできるビザを取得できました。最初は2年の滞在許可証取得で、最初は1年の更新で、その後、4年目からは、就労ビザとなり、3年の更新をしました。
最初の外国人局での対応からドイツ語がだいたい聞き取れていましたので、親子での滞在もできるという柔軟な対応が印象的でした。日本の方が噂されているような状況とはまるで雰囲気が違うのです。子供の教育のために親が仕事をして滞在するのは、ありですね・・という外国人局の対応でした。日本の主人からのサポートがあるなら尚更可能である・・という対応でした。また、大学卒で永住権を希望するならば、社会融合講座(ドイツ語のインテグレーションコース)をビザ取得時にもらうことができるようで、実際に私は社会融合講座をいただき、ベルリッツに通学することができました。
家のことなどは、自力で探したりしていましたが、だんだんと他の申請も自力でもできるようになり、5年目にはKSK保険に加入して、私立保険から国の法定保険に切り替えることができました。
子供の進学と、親の仕事を進めながら、だいたい予定通りに進んでいます。2019年の夏頃から、ドイツ語もさらに進めて、B2コースからはじめて、現在はC1コースを進んでいます。夏から本の商業出版の執筆を進めて、2019年12月には、執筆だけに集中をして、すべてを書き上げました。2020年の1月からドイツ語のC1を進めています。
2020年の2月にベルリンフィルのコンサートの演奏を聴きにいきましたが、その頃から不穏が空気が流れて、世界中でコロナ時代となりましたね。コロナ時代の初期、2020年4月17日に本を出版。普通は、本を出版すると宣伝に奔走しなければいけないのですが、私は全てをオンラインで済ませました。商売のために書いたわけではなく、自分を誇示するために書いたわけでもなく、KSK保険に加入するために執筆したからです。
2021年からSNS時代に突入。ウェブ起業のブログ作りを教えることを始めたり、その後は動画編集も学びましたが、親も色々と学ばなければいけないので大変でしたが、子供はそのままドイツの学校で進んでくれますので、そして、放置しても大丈夫ですので、よかったですが、親子共々大変で、子供に学費がかからない分、親の私に学びのお金がかかるという・・こんな状態であることも面白い点だと思います。
2022年には、私は心理学の勉強をしていまして、アドラー心理学や神経言語プログラミング(NLP)を学び資格を取得しましたが、今後どのように使えるのか・・は、私自身の人生後半の計画にもよるかと思います。そんなこんなのうちに、息子もギムナジウムを卒業して、大学の道へ。
2023年は、また新たな道を模索して進んでおります。
永住権を取得しましたので、仕事の面では自由になり、個人事業主でも就職をしてもどちらでもよい状態ですので、バランスよく両方をしたいと考えていて、今思うことは、ドイツ語の強化が大事であると考えています。
-

-
親子留学10年以上の経験と考察。オーストラリアからドイツへの教育移住のすすめ
『オーストラリア親子留学』からすべてがはじまった・・。 愛する両親、父と母に捧ぐ・・。命を次世代へとつないでまいります。 「教育移住」を、我が子に贈る・・。 我が家は、夫婦で、一致団結して、まずは、『 ...
続きを見る
留学期間について、期間が意味するものメリットとデメリット
ドイツ長期親子移住のメリットとは・・・
- 子供の語学が上達する、英語とドイツ語習得で、トリリンガルになる
- 永住権(無期限滞在許可)をめざすことができる
- 現地の大学入学、就職も可能になる
- いずれは、ご主人さまも定年後に呼び寄せができる
ドイツ長期親子移住のデメリットとは・・・
- 日本に帰国した際、帰国子女試験などが大変である
- 日本の家族と離ればなれになる
- 日本人というより、外国人になってしまう
- 子供の日本語が劣化する
- 日本のテレビや話題に疎くなる
ドイツ数年の親子留学のメリットとは・・・
- 滞在を許可されたら、更新を考えずに数年間滞在できる
- 日本に帰国後、帰国子女試験にチャレンジできる
- 将来的に、子供が自力でドイツに行きたい場合のきっかけになる
- ドイツ語を習得できる
- ドイツのインターにもチャレンジできる
ドイツ数年の親子留学のデメリットとは・・・
- 数年間は、英語もドイツ語も中途半端になりがちである
- 帰国子女試験での受け入れ学校を探すのが大変
- 数年の留学中も、帰国後を考えて、日本の勉強を維持しなければいけない
連邦制国家であるドイツ連邦共和国は限定的統治権を保有する16の州から成り、総面積は357,021km2で、主に温暖な季節的気候に属する。首都及び最大都市はベルリンである。同国はヨーロッパ大陸における経済的及び政治的な主要国であり、多くの文化、理論、技術分野における歴史上重要な指導国である。
出典:ウィキペディア ドイツ
親子留学の考え方、判断の仕方について
ドイツの国にあっているかどうか、将来的にどうするかで判断するのが好ましいです。
- 日本の大学を目指す、日本で就職するなら、数年のドイツ親子留学
- ドイツの大学を目指す、ドイツで就職を希望なら、長期のドイツ親子留学
になります。
また、日本の家族との関係、健康問題、介護問題などからも総合的に判断しなければいけません。
親子留学でドイツで進んでいけるのかどうかですが、こちらもそれぞれの価値観、子供の進み方にもよって違ってきます。
私が思うところでは、日本は競争社会であり、小学校のときから競争をして良い学校、良い大学、良い就職をさせたいと親御さん、お母さんがまず先に考えている方が多いですが、
ドイツのベルリンでいろいろと聞いてみると、(もちろん階級社会ですので・XX家などを除いて)普通の人では、競争なども、学校の良い悪いなどもないと聞きました。競争したいとも思わないとのことでした。
子供さんをドイツで進ませることが良いのかどうか・・お母さんもいろいろとご検討されると良いかと思います。
また、現在私自身がドイツ語の語学学校に行き、いろいろな国から若い方がドイツの大学を目指しているのを毎日目撃していますが、多くの方が積極的にドイツの大学を目指しているのに、日本の方は躊躇されている方が多いのかな・・と観察しています。
日本に帰国後の活かし方(数年の親子留学の方のために)
日本に帰国したら、子供さんは、帰国子女試験にチャレンジしてみましょう。また、英語やドイツ語を持続、維持するようにしてください。
オンラインではいろいろと学べるサイトがあります。PCの中は、英語の宝庫ですね。
カーンアカデミーでは、英語で数学、理科、プログラミング、アメリカ留学のためのSATを学ぶことができるようになっていますので、チャレンジしましょう。
また、14歳以上では、オンラインハイスクールに入学できますので、こちらも有効活用しましょう。
長期ドイツ親子移住、数年のドイツ親子留学、どちらが向いているか?
長期親子移住が向いている人とは、
- ウェブ起業などに意欲がある方
- 海外での経験が少しでもある方
- 健康に自信がある方
- 家族関係が良好で、ご主人のサポートがある方
- 忍耐力がある方
- 子供さんもあきらめずに、進んで行ける方
- 子供さんもドイツの大学、就職を目指す方
- 未知の世界にめげない、チャレンジ精神、サバイバル精神のある方
- 他人に依存しない方
- 楽観的な方、鷹揚な方、細かいことに悩まない方
数年のドイツ親子留学が向いている人とは、
- とりあえず、海外で数年生活してみたい
- 数年の親子留学を日本で活かしたい
- 子供は日本の中学、高校、大学を目指す
- 将来的に、子供が一人でドイツに行くことができるきっかけにしたい
- ウェブ起業をしていく自信がない、勇気がない
- 数年くらいしか、家族、ご主人が許可してくれない
親子留学9年間から観察した、ウェルカムクラス、移民クラスの現状について
2023年に拝見した記事で、ドイツのウェルカムクラスが難民のためのクラス・・・と書かれていたのを拝見しましたが、これは間違いで、かなり古い情報であると思われます。
難民だけでなく、移民が続々と来ていますので、また、先進国からの子供もいますので、ドイツ語が初心者の子供は、ウェルカムクラス(移民クラス)からのスタートになります。
実際に私はウェルカムクラスのコーディネーターとお会いしておりますが、ウェルカムクラス(移民クラス)に入るために、ドイツ語や英語の簡単なテストを行い、クラスを決めているようです。日本の学校の成績表や英語の資格などを求められることもあります。
また、拝見した記事ですが、ベルリンではウェルカムクラス(移民クラス)にて、半年でB1に合格しなければいけないということはありません。これはバイエルン州など厳しい州でのことだと思われます。
大概に日本人は良い成績を収めているのが普通です。中には、ドイツ語ができない子供様もいらっしゃいますが、
私が考えるに、ドイツでうまく進めるためにも、ドイツに来る前に英語ができていることが必須で、
英語圏での学校やインターで3年以上過ごしていることをお勧めしています。
我が家の親子留学は、2011年からですので、9年以上になります。ドイツのベルリンは5年になります。そんな観点からいろいろとながめております。
アメリカ、オーストラリア、ドイツ・・といろいろと違いますね。
また、今まで色々な方とお会いすることができましたので、オーストラリアだけでなく、アメリカ、東南アジア、ニュージーランド、中国の教育の現状などもだいたいわかりつつあります。
ドイツの教育の現状としては、日本のドイツ学園での教育実習、デュッセルドルフのギムナジウムでの体験実習から観察しています。
子供の経験からみると、ほとんどがベルリンでのお話になりますが、(ベルリンを4年間見て来ていますのでその現状です。ドイツは州によって違います。)外国人は、移民クラス、ウェルカムクラスからスタートします。
こちらは、移民や難民を受け入れる最初の1年間くらいのドイツ語の集中コースになります。
12歳以上だとギムナジウムに併設されたウェルカムクラスになります。11歳以下だと小学校の中の移民クラスのようです。
我が家の実際の体験は、12歳以上のウェルカムクラスになります。小学校の例は、お話で聞いております。
12歳以上のウェルカムクラスも学校によってかなり差があるようです。ミッテあたりで先生も真剣に勉強をさせてくれるところもあるようです。
アフリカのシエラレオネからの生徒などもいらっしゃるようで、家庭教師をつけて、ギムナジウムに入学するために真剣に勉強している生徒もいると聞きました。
一方、英語もドイツ語もできないベトナムの生徒もいて、先生も困っていたようですが、それなりに先生がアドバイスをしているとも聞きました。
日本のインターから来られた方で、ドイツ語をすでに学んでおられた方などは、1か月ですぐにギムナジウムに入学された方もいらっしゃいます。
全般的にみると、できましたら、英語圏で英語をマスターしてから、ドイツ親子留学をするのが好ましいと思っています。
我が家の例のように、英語圏3年での親子留学が費用の点でも良いかと思います。そこからドイツ親子留学へと移行することがのぞましいです。なぜなら、英語圏で3年くらいの英語レベルでないと、その後、自力で英語を伸ばしていくことができないからです。
英語圏3年くらいの経験があると、オンラインなどで自力で英語を維持することが可能です。
学校を選ぶことはできずに、住所から最初は移民クラス、ウェルカムクラスを指定されますので、運次第になってしまいます。
その後、1年以上の移民クラス、ウェルカムクラスをすごして、ドイツ語もB1レベルをこえてからなら、ほかの学校に移動するのも可能なようです。
興味深い例だと、17歳で移民クラスに来たチェチェンの女性の生徒は、17歳からドイツ語をはじめて、18歳以上になると、成人になるので、ギムナジウム併設の移民クラスからは離れなければいけないので、
18歳以上のドイツ語の学校に通学して、B1以上をマスターしてから、現在、20歳あたりだと思いますが、どこかの学校の9年生に在籍しているようです。そこから、10年生でMSA(中等教育卒業)をして、その後、進んでいくと思われます。
この例に鑑みて、年齢がかなり遅い??と思われましたでしょうか? 20歳を過ぎて、まだ、中学を卒業していないわけです。
私はそう思いませんでした。チェチェンという国を離れて、20歳で中学くらいだとしても、これから10年をかけて、立派にドイツで働いていくことができると思うのです。
ギムナジウム(ドイツ語: Gymnasium)は、ヨーロッパの中等教育機関。標準ドイツ語では、ギュムナーズィウム[gʏmnáːzium]の発音がより近い。日米の「単線型」教育制度に対する、主に中央ヨーロッパの「複線型」教育制度のいわば根幹を成す存在ともされる。国によって微妙に名称が異なるが、本稿では一括してギムナジウムとする。
高等教育への進学準備を目指す課程であり、イギリスのグラマースクール、シックスフォームカレッジに相当する。日本でいう中高一貫教育に近い。
親子留学で考える子供の教育と親の価値観
私たちは、常に、日本の教育と比べています。特に年齢とその学力などを比べています。そして、難民と日本人は違うと感じられている方も多いかと思いますが、8年前のことを振り返ると同じではないかなとも思うのです。
どんなことでも、考え方次第であり、捉え方次第、心のあり方次第であり、どんなチャンスでもあるということを子供に伝えることが、教育の上で一番大事なことであると思っています。
日本では、そして、日本人的な考え方の多くは、残念ながら、他人に細かいことを指摘する方も多いですし、物事を広く捉えることができずに、いつも窮屈になっている場面も多いと観察しています。
いつも周りを気にして、何かいわれないかとビクビクして、どっちでもいけるような言葉使いで逃げている方も多く、長いものに巻かれろ的な感覚で安心している方も非常に多いです。
そのような親の価値観や考え方が子供の心に伝播して、今の日本の現状があると見ています。
子供のいじめなどの環境は、何気なく、知らずしらずに大人たちが作ってしまった悪い環境なのです。
私が今考えていることは、事実というものはないということです。その方が今していることこそが、事実であり、それは、他の方は違うこともあるということです。
情報などは、参考程度におさえるのは、あたりまえのことであり、多くの方が自分の経験、自分が見た範囲で書いているだけです。
私が8年間ずっとツイッターが面白いなと思って来たのは、権威でもなく、専門家でもない方が、何気なく発言している内容です。その中にこそ、真実があると思っているからです。
いくつかの普通の方の発言を組み合わせて、そこから自分で真意をくみとっていくことこそが、本当のことを捉えることになると思っているからです。
さて、長くなってしまいましたが、比較することからはじまって、物の捉え方についてまで、個人の意見を書きましたが、
子供には、どんな方法でも、どんなことでもできることを伝えたく思っていて、それは、捉え方次第であり、心のあり方次第であるのです。
親の価値観、心のあり方が非常に大事なことがわかります。
2019年春に思う、結局、ドイツで外国人が学ぶことはどうなの?
多くのドイツでの親子留学を希望される方を見てきましたが、子供の年齢にもよって違い、それぞれになりますが、いままで、次のようなケースがいらっしゃいました。
- 英語圏の留学からドイツ親子留学に移行する方
- 日本のインターナショナルスクールからドイツ親子留学に移行する方
- ドイツのインターナショナルスクールに入学する方
- 日本の学校からドイツの現地の学校、幼稚園に入学する方(年齢0歳から16歳まで)
- 日本以外の海外在住からドイツ親子留学に移行する方
みなさん目的もそれぞれで、何をめざしているかもそれぞれになります。
ドイツで勉強をして、日本の大学入学で戻ることを目指す方もいれば、2、3年の滞在で日本の中学に戻る方、ドイツにそのまま継続して滞在する方、ドイツから他の海外に移住する方など、
ドイツでの滞在をいかに有効的なものにするかは、その方によって違ってきます。
親の滞在許可によっても左右されますので、そのあたりは慎重に対処する必要がありますが、子供にとっては、貴重な体験ができる場所でもあります。
ベルリンのインターナショナルスクールに通学されている方がいらっしゃいますが、本当は、資金面では、英語圏と同じになりますので、オーストラリアに行った方が小学生の場合は良いかと考える場合もありますが、
この方は、ドイツ、欧州であるベルリンで子供を過ごさせることに意義があるとおっしゃいました。
そして、音楽ではロシア人の先生をつけるという環境も獲得されています。子供の芸術面での向上に役立つと考えられているのです。これは、オーストラリアでは体験できないことです。
我が家の場合は、私は音楽に関心がありますが、息子はないのですが、オーストラリアよりベルリンに来て良かったと思う点があります。オーストラリアの明るい雰囲気と健康的な面も良かったのですが、息子もチラッと言っていましたが、オーストラリアは留学生でいる間は、ちやほやされますが、就職となると、ちょっと厳しいかなと予想できます。
そんな点では、ドイツのベルリンは、多くの外国人が移民も難民も入って来ていますので、その中にごちゃ混ぜに入り込んで、その一員として日本人が立っていける状況がわずかながら残されていると思うのです。今後、ドイツでの移民背景の割合が30%にもなるようです。
他の西洋諸国でわずかに残されているところがあるでしょうか・・とよく想います。やる気さえあれば、勉強を続けることができますし、わずかながらですが、賢い方は日本人でも入り込んでいけるスペースがあるということです。
しかしながら、ドイツ語を現地の方と同じレベルに持って行くことは大変ですが、できないことはないのです。長い目で忍耐強く、また、子供さんは自力で勉強ができる力を小学生の間に身につけているならば、その後も一人で勉強を進めることができます。
チャレンジ精神が旺盛の方ならば、きっと進むことができると思います。ぜひ、英語をマスターしてから、ドイツ語に移行されてください。
英語をまずマスターしておくことで、自信をもつことができますので、英語は最初に必須であると考えています。
親子留学1年目から9年目までの経緯
下記が親子留学9年目までの経緯になります。
| 親子留学何年目? | 親子留学の場所 | 年齢 | 学校の様子 | 親のビザ |
| 1年目 | アメリカ、ドイツ、オーストラリア | 10歳 | オーストラリア小学校5年生3か月のみ、まだ慣れない | 観光ビザ、ビザラン |
| 2年目 | オーストラリアケアンズ | 11歳 | オーストラリア小学校6年生、1年目で英語の本が読めるようになる | ガーディアンビザ |
| 3年目 | オーストラリアケアンズ | 12歳 |
オーストラリア小学校7年生、2年目で友達がたくさんできる |
ガーディアンビザ |
| 4年目 | オーストラリアケアンズ | 13歳 | オーストラリアハイスクール8年生、3年目でエッセイが書けるようになる | ガーディアンビザ |
| 5年目 | ドイツベルリン | 14歳 | ドイツウェルカムクラス、8年生、ドイツ語B1合格 | 就労ビザ、個人事業主 |
| 6年目 | ドイツベルリン | 15歳 | ギムナジウム9年生、通常授業に慣れる | 就労ビザ、個人事業主 |
| 7年目 | ドイツベルリン | 16歳 | ギムナジウム10年生、MSA合格 | 就労ビザ、個人事業主 |
| 8年目 | ドイツベルリン | 17歳 | ギムナジウム11年生、アビトウアに向けて準備に入る |
就労ビザ 個人事業主 |
| 9年目 | ドイツベルリン | 18歳 | ギムナジウム11年生、引越しの機会に外国人に有効なギムナジウムへ転校、11年生は2回繰り返すのが有効である |
就労ビザ 個人事業主 |
上記のように、
- 9歳まで日本での教育を受ける
- 10歳から英語圏留学をする
- 14歳くらいからドイツに移行する
このパターンが良いのかなと思っています。
親子留学の良いところと悪いところについて
親子留学も良い点と悪い点があります。これらは、人の価値観によって見方や感じ方が変わってきますが、多くの方が一般的に感じる平均的なことを書いてみたいと思います。
親子留学の良いところ
- 親子で海外に滞在ができる
- 子供が海外の学校に通学できる
- 子供が早くから語学を習得できる
- 日本の枠をはずして価値観を変換できる
- 子供にとって将来的に有益である
- 親にとってもサバイバル経験ができる
親子留学の悪いところ
- 夫、ご主人を日本に残していること
- 家族が離れていること
- 高齢の両親、義理両親が心配になること
- 病院など、いざとなったときに不安である
- 子供の進学の問題、帰国のタイミングが難しい
- 知り合いやネットワークが少ないこと
つまり、親子留学の悪い点を1つづつ良い方向に転換していくことが大事になります。
上記から取り上げてみると、
- 夫、ご主人を日本に残していること
これについては、物理的に距離が離れていても、スカイプをつないで、時差を利用して家族といつも話すことができるようにしていく対策が大事になります。
2番目の高齢の両親、義理両親についても、スカイプで逐一状況がわかるようにしておく必要があります。
- 病院など、いざとなったときに不安である
こちらについても、前々から準備をしておく、健康オタクになっておく必要があります。
- 子供の進学の問題、帰国のタイミングが難しい
こちらも、日本を出国するときから、いくつかのパターンで計画をする必要があります。
- 知り合いやネットワークが少ないこと
こちらも、ネットワークを広げるか、もしくは、少ない人間関係をよいものと考える価値観の変換が必要です。
親子留学における親のチャンスの広げ方と子供の成長
親子留学において大事な点は、親が価値観を変えて、日本にいるときよりお、もっと広い視点で多くのチャンスを捉えるというところだと考えています。それは、子供にも伝播していきます。
お母さん、親のチャンスの広げ方としては、海外の語学学校から大学に進む、仕事をする、起業をするなどになります。子供を見守りながら、チャンスを広げていくことができるのか、または、日本に帰国しても、活かしていけるのかが大事になります。
私も実際に、親子留学をすることによって、ビザの関係などで、何かを作り上げていかなければいけないという環境に強制的に置かれたことになります。その中で、ブログを作成したり、自分独自のものを立ち上げたりしてきました。
2019年は、さらに本の執筆をすることにまでつながり、やはり、自分で作っていくことが大事であると思っています。今後も同様にさらに進めなければいけないのですが、同時に語学の方も進めなければならず、ドイツ語の語学学校に通学しながらブログ作成の方なども進めています。
そんな中で、子供の方は着々と学校が進んでいきます。子供を見守りながら、そして、余計なことを言わずに、陰ながら応援しながら、そして自分の仕事も進めていくという、華やかではないですが、堅実な進み方は非常に良いと考えています。
なんといっても、大事なのは、子供の成長であり、進学であり、いずれは、子供がしっかりとした自分なりの仕事を持つことです。そのためになら、親、お母さんは、柔軟に、臨機応変にいつでも動けることが大事であるとわかり、そして、子供のことを第1にして進めていくことで、親子ともに成長ができると思います。
2020年4月17日に『子供と一緒に飛び発とう! 親子留学のすすめ』を刊行して、さらに親子留学について考えること・・
4月17日に本を刊行しまして、5月22日に朝日新聞の広告にも掲載しまして・・
本を読んでくださった方からの感想などもいろいろ聞きながら、
意外にも、ブログよりも本を読んでくださっているお父さま方も多いのかな・・なども・・。
最近思うことは、もっと自由に、多くの方が気軽に親子留学ができれば・・
このように思うのですが、なにか多くの雰囲気が重いというか・・
検索して出てくるブログの内容も、重いものも多いですしね・・
私の経験では、親子留学はもっと気軽なものでよい・・と思っています。
よくよく検討していては、動けないですし、波に乗る調子でよいのです。
我が家も、ただただ、波に乗って来ただけですので。
よく考えて、検討して・・のアドバイスに従うと、動けないで終了です。
まじめはよくない、真面目にならないと・・本質をつかめ・・ですね。
多くの方は、まじめすぎるのです。重い考え方が多いのです。
重い考え方とは、ネガティブな考え方のことです。
親にサポートをしてもらって、どんどん親子留学ができるといいですね。
親にも応援を依頼するべきである・・とも思っているのです。
子供の適齢期は、限定的なものですので。
-
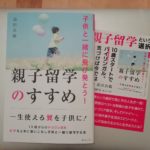
-
子供と一緒に飛び発とう! 親子留学のすすめ 一生使える翼を子供に! 10歳からのバイリンガル
2020年 4月17日に、 『子供と一緒に飛び発とう! 親子留学のすすめ 一生使える翼を子供に! 10歳からのバイリンガル』を刊行しました。 ...
続きを見る
2020年6月の最新情報 親子留学からドイツ医学部への道!
2020年のドイツの高校卒業試験(アビトウア)で、ドイツの移民クラス、ウェルカムクラスから医学部への道を拓いた生徒がいることがニュースでも報道されました。
こちらに書きました。
-

-
ドイツ・ベルリンのウェルカムクラスから、ギムナジウム、医学部へ
昨日ニュースでも流れたようですが、 ドイツのウェルカムクラスからギムナジウム、 そして医学部へと進む生徒が出現・・ アビトウアの点数は、1.1 のようで、がんばったのですね!! 先 ...
続きを見る
上記の例を参考にして、ドイツの医学部への道を拓くには、(ベルリンの例ですが・・)
(この生徒はパレスチナ人で、どこまで英語ができたのかがわからないのですが、日本人の場合は、事前に英語ができた方がいいでしょう)
- 10歳から親子留学で3年間、英語に集中すること
- 13歳、14歳からベルリン入りして、ウェルカムクラスからドイツ語をはじめる
- 1年後に、ギムナジウムに入学する 成績のためにも移民80%以上のギムナジウムがおすすめです
- 11年生、12年生で満点近くの成績をとり、1.0 から1.2 の結果を出すこと
上記で、医学部の道を拓くことができます!
最新情報! 2021年 永住権(無期限定住許可・EU滞在許可)を取得
また、詳細はのちほど、記載いたしますが、
2021年にドイツ永住権・EU滞在許可を取得いたしました。
2015年の6月からビザ・滞在許可を取得していますので、
6年目での取得になりました。
先に学生ビザで息子の方が永住権取得となり、
その後、私の取得となりました。
こちらも参考になさってください。
ドイツのFederal Office for Migration and Refugees のサイト
危機管理のために、在ドイツ日本大使館の安全の手引き 改訂版より
-

-
親子留学と短期親子留学のメリットとデメリットについて
留学情報などは、一般的に良いことしか書かれていないと、よく言われます。 親子留学についても、良いことしか書かれていない場合が多いですね。 私はすべて本音で我が家が経験したことを書いていま ...
続きを見る
-

-
サービス紹介
サービスのご案内 スポットアドバイス 親子留学、教育相談のための最初のスポットアドバイスです。どんなことでもご相談できます。 詳細はこちら 親子留学のための教育相談 1年前 ...
続きを見る
さらに詳しく知りたい方は、メルマガもご登録ください。
